EOLとは?放置することのリスクや情シスが行うべき対応について
本記事では、EOLの概要やEOLを放置することのリスク、情シス部門がEOLに備えてやるべきことを解説します。
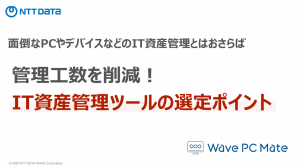
IT資産管理ツールの選定ポイント
EOLとは
本章ではまず、EOLの概要やEOS/EOEとの違いについて解説します。
EOLの意義・必要性
EOLとは、End Of Lifecycleの略で「ライフサイクルの終わり」という意味であり、ITの分野ではハードウェアやOS、サーバー、ソフトウェアなどの生産、販売、サポートが終了することです。製品、機器として寿命を迎え、新たに更新されることがないため、そのまま使い続けることが難しくなります。
メーカーがEOLを設定する主な理由は、製品や機器の経年劣化に伴う安定性の低下や故障リスクの増大を防ぎ、ユーザーに安全かつ信頼性の高い運用環境を提供するためです。さらに、技術の進歩により既存の製品・機器が市場の要求に適合しなくなることを見越し、より高性能で効率的な後継モデルへの移行を促進する目的もあります。これにより、メーカーはサポートの効率化を図り、最新技術を活用した製品の開発・提供に注力できるようになります。
安定した業務を遂行するためには、製品や機器の寿命を把握し、EOLを迎える前にシステムの更新や移行、製品の入れ替えを行うことが必要です。EOLを迎えた製品・機器は技術サポートが受けられなくなるため、セキュリティ対策やコンプライアンス順守の観点から、そしてビジネスの継続性を保つためにもEOLに関する正しい知識を持つことが不可欠です。
EOSやEOE、EOSLとの違い
EOLに類似の用語・概念として、EOSやEOE、EOSLがあります。
EOS(End Of Sales)は「販売終了」という意味であり、製造元メーカーが製品や出荷・販売を終了することを指します。あくまでも新規購入ができなくなる時点のことであり、サポート自体は一定期間受けることができます。
EOE(End of Engineering)とは、製品に対するテクニカルサポートの提供が打ち切られるという意味です。具体的には製造元メーカーによる不具合の修正や新規のアップデートが行われなくなる時点を指します。
EOEではテクニカルサポートが制限を受けるのに対し、EOLではすべてのサポートが打ち切りとなります。
EOSL(End Of Service Life)とは、製品のサポートや保守サービス期間が終了することです。いわゆるサポートの期限切れを意味し、EOSLを迎えると実質的にサービスが利用できなくなります。EOSLはEOLと基本的には同義ですが、EOLはハードウェアだけでなく関連するソフトウェアのサポート終了も意味し、より広い意味合いで使われることもあります。
EOLの一例をあげると、Windows10は2025年10月14日にサポートを終了するので、それまでにWindows11へのアップデートが必要です。
EOLを迎えるとどうなる?
EOLを迎えるとメーカーから一切のサポートが提供されなくなり、以下のような状態になります。
・不具合の修正やアップデートの停止
EOL後の製品では、新たに発見されたバグや脆弱性に対する修正プログラムやアップデートが提供されなくなります。
・製品の修理対応やサポートの終了
メーカーによる技術サポートや保守サービスが完全に終了します。これにより、トラブル発生時に公式の問い合わせ窓口が利用できなくなるほか、技術的な質問への回答が得られなくなります。
・部品の製造・調達が困難になる
EOL後は製品の部品の新規生産が行われなくなるため、故障した部品を製造・調達できず、交換が困難になります。その結果、製品の修理や保守が難しくなります。
EOLを放置することにより発生するリスク
EOLを放置すると、セキュリティ面や生産性、互換性の面で問題が生じます。
セキュリティリスクが増大する
EOLを迎えると脆弱性に対する修正が行われなくなるため、ウイルス感染や不正アクセスなどの被害を受けやすくなり、セキュリティ面で深刻な脅威にさらされます。
脆弱性を突いて情報を窃取しようとする悪意ある者にとって格好の的となり、重大な情報漏えいの被害のリスクも高まります。
生産性が低下する
EOLを迎えた製品は、最新の製品と比べて機能・性能が劣っている、経年劣化により故障率が高くなっているなどの理由から業務効率やパフォーマンスが落ち、生産性の低下につながります。
さらに、故障した場合にはサポートを受けられないため、修理・復旧まで非常に長い時間を要したり、あるいは復旧自体ができなかったりするケースも少なくありません。このことも当然、生産性の低下を招きます。
互換性の問題が生じる
最新のOS環境で正常に動作しなくなったり、現在普及しているソフトウェアとの互換性に問題が生じたりします。これにより、業務に必要なソフトウェアやシステムとの連携が取れなくなる可能性が高まります。また、新しいハードウェアやソフトウェアと接続できない、またはデータの移行が困難になることもあります。その結果、業務の効率が著しく低下し、プロセス全体に支障をきたすことがあります。
EOLに備えて情シスがすべき対応
EOLを放置せず、適切にリプレイスするためには、情シス部門が入念な事前準備を行っておくことが大切です。具体的には以下の対応をとる必要があります。
EOLの情報を整理する
最初に行うべきことは、自社が保有しているハードウェア、ソフトウェアの棚卸を行い、自社のIT資産全般の状況を把握することです。特に以下の情報を整理し、資産台帳やインベントリ管理システムに登録します。
・導入しているハードウェアの製造打ち切り時期
・ハードウェアの製品名・型番
・保守契約の有無 など
IT資産管理ツールを活用して情報を整理する必要がありますが、加えて購買情報や契約情報などの確認も必須です。
また、製品の公式ウェブサイトやサポート文書などからEOLの情報を入手し、EOLの正確な日付、サポート終了のスケジュール、推奨される移行先などの情報を製品ごとに整理します。メーカーサイトに記載されている部品の保持期間についても、確認する必要があります。
それらの情報をカレンダーに登録しリマインダー設定をしておくと良いでしょう。
EOLを迎える前にリプレイスの計画を立てておく
EOLの時期が迫ってから慌てて対応すると、移行作業が間に合わなくなる可能性があり、ミスが発生しやすくなります。そのため、余裕を持ったリプレイス計画を立て、移行スケジュールを社内に周知することが重要です。具体的には、移行のスケジュールを設定し、人員、時間、予算面で十分なリソースを確保します。その際にはエンドユーザーを巻き込む必要があります。
また、システムをアップグレードすることで影響を受ける可能性のあるアプリケーションや互換性の問題を整理し、システムが正常に動作するかを確認するためのテストスケジュールも組み込んでおくべきです。
リプレイスにかかる費用を見積もっておく
新しいハードウェアやソフトウェアの購入費用、データ移行やシステム構築にかかる費用などを試算し、さらに移行作業に必要な人件費も見積もっておくことが重要です。適切な費用見積もりを行うことで、経営層への説明や予算確保がスムーズに行えるようになります。
第三者保守を活用する
第三者保守とは、サポート期間が終了した製品・機器に対して、専門技術や知識を持つ第三者の企業や機関が保守サポートを提供するサービスのことです。リプレイスまでの期間が短い場合には、第三者保守を活用することで一定程度時間を確保することができます。
EOLへの備えとしては以上の対応をすべきですが、すべての工程を自社で行うのは大変です。そこで、アウトソーシングを活用することも1つの選択肢となります。
次章では、法人PCにおける運用管理を任せられるサービスをご紹介します。
法人PCの管理はWave PC Mateにご相談ください
Wave PC Mateは、PCの調達・導入から運用管理、廃棄までをトータルでアウトソーシングできるサービスです。OSやウイルス対策ソフト、各種ソフトウェアの更新処理を任せることができ、OSアップデートや移行にかかる時間、労力を代行します。これにより、本来の情報システム業務に注力できるようになります。
特に、Windows Updateの適用、ウイルス定義ファイルの更新などの業務は、社員数や拠点数や多ければ多いほど膨大な工数とコストがかかります。Wave PC Mate をご利用いただくことで、これらの更新業務から解放され、システム管理者の負荷を軽減でき、コスト削減にもつながります。
契約期間は3・4年のコースと決まっているため、「気づいたらEOLを迎えていた」という心配もありません。
さらに、2025年に迫るWindows11への移行もWave PC Mateならサポート可能です。
Wave PC Mate によるWindows11へのアップデート・移行サポートの詳細については以下をご覧ください。
以下の資料では、管理工数を削減するIT資産管理ツールの選定ポイントを解説しています。こちらもぜひご覧ください。
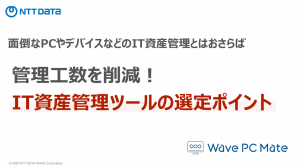
IT資産管理ツールの選定ポイント

- Wave PC Mate 運営事務局
- Wave PC Mateは、NTTデータ ウェーブが提供するハードウェアの調達から導入、運用管理、撤去・廃棄までのPCライフサイクルマネジメントのトータルアウトソーシングサービスです。本サイトでは、法人企業のPC運用管理業務の課題解決に役立つ様々な情報をお届けします。
の代行.png)
